『静と義経』のタイトルロール「静」は、このオペラにおいて存在感が大きく、責任を感じている。三木稔先生、なかにし礼先生の渾身作であるだけに、体力、集中力、気力を養い、静についての研究も深めて表現したい。共演者は、気心知れた方々も多く、層が厚くて頼もしい。3月2日のチームとも協力しあいながら、一丸となって三木先生の想いの結晶「三木マーク」をはじめとする美しい音楽をつくりあげていきたい。大学時代から日本の作品が好きで、最初から日本オペラを目指して歩んできた。美しい日本語を後世に残したいという使命感もあり、自主公演やCD発売など、活動に熱が入る。
今最も旬なアーティストのリアルな声や、話題の公演に関する臨場感あるエピソードなど、オペラがもっと楽しめること請け合いの情報をお届けするコーナー「CiaOpera!」。第30弾は、前回の楠野麻衣氏に引き続き、2019年3月3日に『静と義経』に静役で出演される沢崎恵美氏。タイトルロール「静」や作品への意気込み、美しいアリアについて、共演者について、ここまでひと筋に活動されてきた日本作品についてなどを伺いました。
タイトルロール「静」の存在感を表現する、使命と責任。
ー今日も、まずは沢崎さんが2019年3月3日にご出演の日本オペラ『静と義経』についてお話を伺いたいと思います。沢崎さんはタイトルロールでもある「静」を演じられるわけですが、今の意気込みをお聞かせいただけますか?
はい、まずはなんといってもこの作品、作曲は三木稔先生、それから台本はなかにし礼先生の渾身作。なかにし先生は常々「グランドオペラ」と称されていますし、「オペラに対する僕の想いがすべて入っている作品なんだ。」とおっしゃっています。『静と義経』とタイトルにはありますが、『静』と呼んでもいいのではないかというぐらい、「静」はほぼすべてのシーンに大きく関わりますし、いつもの日本オペラと違い、メロディーとか言葉とか思いを“歌い上げる”ことが重要になってくると、自分では感じています。それに耐えうる体力と、集中力と、気力が必要ですし、責任も感じるなと思っています。

ー静はほぼすべてのシーンに関わるのですか!このオペラにおいて、とても大きくて重要な存在なのですね。
歴史上でみると、静という人物はあまり文献などで残っていないのですよね。私も探してみたのですが、表立って出て来るものはあまりなくて。歴史書『吾妻鏡』『義経記』などに少し登場しますが、静がクローズアップされた資料ではない。そんな資料も少ないなかで、タイトルの頭に「静」が来ているところ、『義経と静』という順ではないところに、この作品における静の使命というか、存在の大きさが集約されているのかなと感じます。
ーこの時代は確かに、女性がフォーカスされるということはかなり少ないのかもしれません。そういった人物の役づくりは、難しい部分もおありなのではないですか?
そうですね。もちろんなかにし先生の台本を読ませていただいたり、演出の馬場紀雄さんともディスカッションはしているのですが、研究書は少ないと言いながらも、インターネットだったり小説だったりを自分なりに調べるようにもしています。今回なかなか参考になると思える一冊があるのですが、角川スニーカー文庫から出ている『静−幻夢義経記』という小説です。その本によると、静はやはり巫女ではあるのですが、それが日本の原始からの流れを汲む巫女で、母の磯禅師からその秘儀を受け継ぎ、義経の師である鬼一法眼が放つ陰陽師のまじないなどから義経を守り、そのなかで恋に落ちていく、というようなことが書かれているのです。なので、もちろん台本にはないですが、そういった義経との出会いのなかに、愛の深さがあるのかなと。また、西洋のキリスト教などでも同じようなことはあると思うのですが、巫女は神様と通じなければいけないので、男性と通じてしまったら罪であるとか、力を失って死んだ同然となってしまうとか。そこもあると思うのです。そういった、背景に抱えたものをどうやって表現していくかを、自分のなかで模索しています。
ー静と義経の出会い、という視点は考えたことがありませんでした!では、今回静という人物を演じる上でポイントにされている部分はありますか?
でも、自分のなかにスッと落とし込めている部分はあるのです。というのも、私自身も結婚して夫がいて、子供もいて、義経のように別れ別れになっているわけではないですし子供も亡くしてはいないですが、「あぁ、この大事な人がいなくなったとしたら」とか、「わが子が…」とか、自分のなかの「女性」や「母性」と照らし合わせて分かるところもある。あまり自分とかけ離れた人物というよりも、自分のなかにあるものと重ねながら静をつくっていけたら、と思います。
実は記者会見のとき、「今の若い人には、『静』についてあまり知られていないのではないでしょうか。」というご質問を受けたこともあり、それで私なりに先ほど言ったような文献・資料をいろいろ探してみたのです。そうしたら、インターネットで見つけた情報ではありますが、静と義経の話を題材にした漫画が出ていて、それが結構人気のようなのです。もちろん脚色されたストーリーではあるでしょうが、もしかすると若い方たちはそういったところから、身近な物語として知らず知らずのうちに歴史に触れているのかな、と思いました。それに、今回のオペラでは静も義経も死んでしまい、来世で一緒になりましょう、というような終わりかたではありますが、その来世についても義経がチンギス・ハンに生まれ変わったとか、実は子供は死なずにいてその後活躍したとか、今でもいろいろな創作がなされているので、劇場に観に来てくださったお客様もそんな風にふたりの来世についていろいろな想像力をかきたてられるような終わりかたを届けられたら素敵だな、と思います。

チーム一丸となって、三木稔先生の音楽と想いをつくりあげる。
ー今回、静のひとつの見せどころでもあると思うのですが、オペラ後半に美しいアリアがありますね。
はい、正直大変です!ここでこのアリアか、という感じに。もちろん、そこに至るまでもところどころ要素は散りばめられていますが、ちょっと沖縄的というか、「別世界」という表現を三木先生がしていらっしゃる曲ですね。そのアリアは、やはりこれまで取り組んできた日本オペラと少し違うような、お客様がお帰りになるときに口ずさんでいただけるような、心に残るメロディーでもありますし、私自身そんなお客様へ届く歌い方ができたらいいなと思います。一方、アリアではない部分でも、語りと歌とのバランスをいかに自然にとるかという工夫も必要ですよね。日本語なので、言葉が分かるだけに難しくもありますが。
ー以前、『よさこい節』の際にも、日本語ならではの難しさについてお話しくださいましたが、今回の『静と義経』でも、やはりその点は追求されるポイントなのですね。
そうなると思います。
ー今回共演者のみなさんとは、何度かお仕事をご一緒されていますか?
もう、気心知れた方々です(笑)。もちろん、なかには初めてご一緒する方や久しぶりの方もいらっしゃいますが、本当に層が厚くて頼もしいです。稽古場も楽しいですし、チーム一体となっている感じがすごくあります。そこは、やっぱり日本オペラ協会のいいところですね。義経役の中鉢聡さんは安定の相手役ですし、頼朝役の清水良一さんとも前回の『よさこい節』では恋人役、今回は敵同士と、よくご一緒しています。劇中、一番密に関わるのは静の母「磯の禅師」の上田由紀子さん、そして先輩方が脇をしっかり固めてくださっています。先ほどもお話したように、静は“チーム義経”と呼ばれる義経・弁慶・佐藤忠信などのシーンにも、“チーム頼朝”と呼ばれる頼朝・政子・大姫などのシーンにも登場しますが、政子役の東城弥恵さんや大姫役の鈴木美也子さんとは、勢力図としては敵でありながら、敵味方関係なく女として共感しあっている部分も出していけると、ドラマがより深まるかなと思います。また、“チーム静”として3月2日組の坂口裕子さんともタッグを組んで、お互い協力しつつ仲良くさせていただけているのが、大変ななかでも「はぁ〜」と気が重くなりすぎずにいられる要因かなと思います(笑)。

ー今回は一緒にお稽古をされているのですね!
そうですね、坂口さんがとても努力家でいらっしゃるので、「見習わなくては」と思いながらやっています(笑)。また、私が出演する3月3日というのは、日本オペラ協会の前総監督でいらした故・大賀寛先生のお誕生日でもあるので、チーム一同そのことへも思いを馳せ、郡愛子総監督のもと、目下頑張っています。
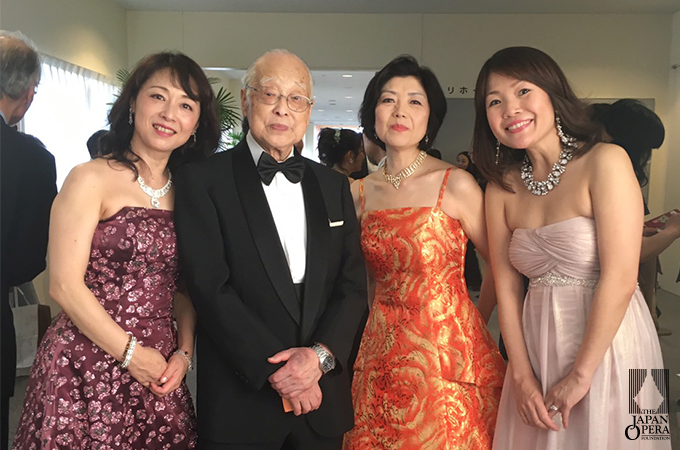
ーそれは、お気持ちもさぞ奮い立つこととお察しします。音楽的には、指揮者の田中祐子さんといろいろ詰めていらっしゃるところかと思います。
はい、でも音楽、難しいですね。楽譜に「三木マーク」と呼ばれる「M」と書かれている部分があるのですが、特にこの表現が難しくて。意味合いとしては「リベロ(自由に)」に近いのですが、大元に流れているリズムも感じながらの表現がとても難しいので、田中マエストロと一緒につくりあげているところです。
ー「三木マーク」という、独特の表現があるのですね!それは、こちらから観ていて、「歌い手がこんな表現をしていたら三木マーク」と具体的に分かるようなものなのですか?
いえ、オーケストラが流れているときもありますし、いきなり歌が出る箇所もありますし。そこでどういった気持ちをつくるかとか、言葉の運びをするかで全然表現が変わるので、そこをつくっていく作業は大変ですね。“間”なんですけど、かといって開けすぎてもいけないというか。演奏する側に委ねられる部分でもありながら、三木先生からの想いを受け止めて表現しなければいけないという点が難しさといえます。
ーなるほど、私たち観客から観ていて「ここだ」と分かるものでもないのですね。例えば、シーンでいうとどんなところで表現していますか?
そうですね、結構たくさんあるのですが、なにか人物の気持ちが動くところかもしれません。例えば静が義経にすがっていくところであるとか、静が無の世界に入っていくところとかですかね。でも、逆にお客様に「あ、いま三木マークを表現しているな」と気付かれてしまっては、負けな気もしています!歌い手としては、「ここはもう1拍歌い込みたい!」とか、「ここ、少し休止になるのでは」と内心感じてしまうようなせめぎ合いがあり、感覚的に自分のなかに落とし込めずに四苦八苦しているところではありますが、説得力のある表現となってお客様へお届けできればいいと思います。

ーそうなのですね!では、詳しくは秘密でしょうが(笑)、私たちも観ていて「気持ちが動いたな」という場面で三木さんの想いをキャッチできたら幸運ですね。演出の馬場紀雄さんとも、そのあたりはつくりこまれていますか。
はい、馬場さんは「基本的に初演を踏襲する」ということをおっしゃっていますので、歌い手としてもその方針に沿いつつ、そのなかで自分たちらしさも表現していきたいです。
ー深みがあり、見所も多そうなオペラですね!拝見できるのが待ち遠しいです!
日本作品への愛、日本語への思いが、幅広い活動へと駆り立てる。
ーところで、沢崎さんはデビュー以来ずっと「日本オペラ」に関わっていらっしゃいますね。
はい、私はもともと日本の作品が好きだったのです。もしかしたら以前もお話したかもしれませんが、いつか『夕鶴』がやりたいという思いもあり、大学を出てどこか団体に所属しようと考えたときも、日本オペラ振興会に日本オペラ協会があるということで、最初からそこを目指して研修所に入ったのです。

ー最初から日本オペラの世界を目指していらしたのですね!
そうなのです。もちろん最初は知識もそこまで深くなく、漠然と「日本の作品が好きだな」というぐらいだったのですが。主人とも研修所で出会いましたし、その主人が「留学に行く」というので私自身もイタリアへ留学して、西洋オペラにググッとシフトした時期がありましたが、根底にはやはり日本オペラへの思いがあって。イタリアから戻ってきて、オペラ『山椒太夫』のオーディションを受けて「安寿」の役をやらせていただいたのを最初に、そこからずっと使っていただいて。ありがたいことですね。今とは違い、当時は研修所を修了すると、藤原歌劇団か日本オペラ協会か所属先を選べたのですが、藤原歌劇団を選ばれる方がやはり多いなか私は日本オペラ協会を選んで、大賀先生には「おぉ、自分から日本オペラ協会を選ぶとは」と思われていたみたいです。
ーそうなのですね。イタリアへ留学されていたときは、もちろん西洋オペラも勉強されていたのですよね?
私は声も軽く、イタリア人の先生に「ピッコリーナ、ピッコリーナ(おチビちゃん)」とか、名前の「めぐみ」をもじって「レグミ(お豆ちゃん)」といって育てていただき、王道のイタリアオペラや、声質に合ったフランスオペラなども教わりました。『カルメン』のミカエラ、『ラ・ボエーム』のムゼッタ、『ラ・トラヴィアータ』のヴィオレッタ、私の声にとっては少し重いですが、日本人の役ということで『蝶々夫人』も小さな会で歌ってみたことはありますし、オペレッタも歌いました。
ーなるほど。そんな勉強を経ても、やはり日本オペラに惹きつけられるという、その魅力とはどんなところなのでしょうか?
今、お客様のほうでも西洋のオペラをたくさん聴いて、勉強されて、作品の内容を分かって聴きに来られる方がたくさんいらっしゃると思うのです。私たち歌い手も、たとえそれがイタリア語など、お客様にすべての意味は分かっていただけないかもしれない言語であっても、内容を伝えるという行為は同じだと思います。でも、もともと音楽の始まり自体が「祈りの言葉」というようなところから来ていて、それがだんだん発展していくのですね。ですので、自分の持っている母国語で、思いと音楽とをリンクさせて伝えることができる日本の作品って、やはり素晴らしいと思うのです。昔から日本の作品というのはどうしても、西洋の音楽を取り入れてはいても下に見られがちなところがありました。けれど、きちんと西洋の美しい発声に乗せながら、普段生活で使っている言葉を“心地よく”伝えるという活動をしているのが日本オペラ協会ですし、素晴らしいことだと感じます。そうは言いながら、日本語にもどんどん新しい言葉や造語が生まれ、若い人たちが「鼻濁音」を使えなくなっているという話も聞きますし、「美しい日本語」というものが失われてきている危惧を感じることがあります。私自身、そんな今を生きていて新しい言葉を使うときもありますが、古典作品などを通して、日本語にもともとある美しさやリズム感などを後世に残していくという使命感も持っているのです。そんな意味でも、ここまで日本の作品に携わり続けてきました。
ー音楽だけでなく、言葉を伝え残していくことへも使命を感じていらっしゃるのですね。
はい。私が主人と結婚する前から主催している、地元横浜で自主公演しているオペラがありまして。それはちょっと地元への恩返しとしての意味もあるのですが、小さな芝居小屋で(馬蹄形のホールです)、未就学児もOKにしたり、オペラにほとんど馴染みのない方でも見やすいように、全曲やると長いので主人が上手につないでハイライト版にしたりして、『カルメン』『魔笛』『こうもり』『ヘンゼルとグレーテル』なんかをやってきたのです。言葉も、日本語で歌って。そうすると、演目によっては親子3世代でいらっしゃるお客様がいるんです、「昔見たのが懐かしくて、みんなで来たよ!」と。楽しみに待っていてくださる。そんな風にヨーロッパの作品でも日本語で歌わせていただく機会があると、自分でも「あれ?私留学してたよね?」と思うこともあるのですが(笑)。でも留学って、今こうやって日本語で歌うための下地にはすごくなっているので、活きていると思うのです。先ほども言いましたが、やっぱりどんな言語であれ、そこに含まれている背景や気持ちを語って、伝える要素って必要で、その基本を留学では学べたのかなと思います。

ーなるほど、根底は同じなのですね。それにしても、日本語を通して音楽を届ける活動を幅広くされているのですね。日本語と音楽、どちらへの思いも伝わります。
こんなに日本語ばかり歌うか、とも思いますけれどね(笑)。実は金子みすゞさんの詩に中田喜直さんが作曲した歌を集めた、『ほしとたんぽぽ』というCDも出したのです。私もひとりの歌い手として、自分の活動の証を残したかったということもありますけれど。
ーCDも出されたのですか!金子みすゞさんの世界、あたたかいですよね。
はい、ずっとやりたいと思っていた企画で、こうして形になったのです。伴奏は、竹村浄子さん、ジャケットの絵は私の娘が描きました。金子さんの詩は、わが子への思いが美しい日本語でつづられていて、そこに中田さんが寄り添うように曲をつけている。あたたかい、日本の原風景のような世界のなかで、生と死も考えさせられる。日本語がもともと持っているリズムとか、表情などの味わいを、朗読と共にみなさんへ届けられればいいなと思ったのです。

ーこれは、沢崎さんだからこそ表現できる世界ですね!こうして沢崎さんの表現を通して改めて気付かせられる日本語や日本の音楽の魅力、日本人だからこそ、ひとつひとつ大切にしていきたいものです。
聞いてみタイム♪
アーティストからアーティストへ質問リレー。
楠野麻衣さんから、沢崎恵美さんへ。
ーアーティストからアーティストへの質問リレー、今回はもうひとチームの「大姫」楠野麻衣さんから、「静」沢崎さんへの質問ですね。
ー歌のお仕事のみならず、良き妻、良き母として家庭のこともきちんと両立されている、尊敬すべきプリマドンナの沢崎さん。常々ご家族思いでいらっしゃいますが、もし一ヶ月、一人きりで自分のことだけを考えて、自由に暮らせる時間があるとしたらどんな風に過ごしたいですか?
まず寝たい(笑)!誰にも邪魔されず、自分の睡眠をとりたいですね。そして、もっと長く譜面と台本に向き合う時間をつくりたいなと思います。あとは、自分のなかの知識を深めるために映画を見たり、本を読んだり、ちょっと旅行にも行ってみたいし。自分の引き出しを増やすための時間がほしいですね。本当は、つくろうと思えばいくらでもできると思うのですけれど、どうしてもなにかをやっていても「あ、ごはんの時間だ!なんとかしなくちゃ!」となる。そうではなく、自分の向き合っていることにどっぷり浸かれるというか…でも、それも飽きちゃうかな(笑)。
ーすごいですね、自由な時間が出来たとしても、やっぱりご自身の音楽にとって肥やしになるようなことのために使おうと思われるのですね。
寝ていることも多いと思いますけれどね(笑)。でも、こういうお仕事をさせていただいていると、もちろん母であり、妻の時間もありながら、こうして家の外へ出て、一個人の歌手・沢崎恵美としていられる時間もあるので、やはりそれってすごく幸せなことだなと思うのですよね。とは言いつつ、やっぱり自分の原点に戻るような時間に当てられたらいいなぁ、なんて思います。ちょっとかっこいいこと言っていますけど(笑)。友達にも会いたいし。おいしいものも食べたいし。要するに、人間としての欲求です!

ーはい(笑)。でも、ご自身と向き合う時間にというご意見、素直に素晴らしいと思います。ありがとうございました。
取材・まとめ 眞木 茜
