ヴェルディのオペラのプリモ・バリトン役(主役)には毎回“壁”がある。オペラ『リゴレット』のタイトルロール・リゴレット役は今まで自分のレパートリーの中でも一番歌わせてもらっている役だが、重ねれば重ねるほどいつも音楽と演技のバランスという難しさが立ちはだかる。それはヴェルディのオペラが本質を描いているがゆえであり、歌だけでなく演じ手としての技量も求められる深い表現に挑むことは、やりがいでもある。逃れられない運命を背負ったリゴレットの人生や、娘を思う父の気持ち。今出来る最高の表現を目指したい。そこには、長年にわたるイタリア滞在で得た学びも、きっと生きてくる。
今最も旬なアーティストのリアルな声や、話題の公演に関する臨場感あるエピソードなど、オペラがもっと楽しめること請け合いの情報をお届けするコーナー「CiaOpera!」。第39弾は、2020年2月1日(土)、2日(日)に東京文化会館で上演の藤原歌劇団本公演『リゴレット』で、タイトルロールを務める上江隼人氏。回を重ねるごとに進化するヴェルディ・オペラについてや役づくりのポイント、共演者、長いイタリア生活で会得したものなどのお話を伺いました。
何度目のリゴレットでも、今の自分に出来る一番いいもので臨みたい。
ー今日は、来年2月1日・2日に上演の藤原歌劇団本公演『リゴレット』にて、2日にタイトルロール(オペラのタイトルになっている役)であるリゴレット役を務められる上江隼人さんにお話を伺います。まずは、みなさんに最初にお聞きする質問ですが、今回のリゴレット役に臨むにあたっての意気込みをお願いいたします。
はい。オペラ歌手っていろいろ声種があると思いますが、なかでもバリトンがタイトルロールを演じる機会というのがあまりないため、そのような機会があることがまず光栄なことだと思います。バリトンのタイトルロール、ヴェルディのオペラだとまだ多い方だと思うのですが、他の作曲家になると数が少ないですからね。それに、『リゴレット』はヴェルディの作品のなかでも特に中期作品の核となるものだと思うので、それを歌わせていただけることは大変ありがたいことです。

ーヴェルディのオペラのなかでも核となる作品なのですね。上江さんは、このリゴレット役はもう何度も歌われていますよね。
海外公演を含めて、10回ぐらい歌わせていただいているでしょうか。世界的な歌手たちは本当に何十回、何百回と歌っているので、それに比べたらまだまだですけれど、それでもありがたいことですね。でも、ヴェルディを歌うときは毎回壁が立ちはだかるのです。それを乗り越えられるか、乗り越えられないかという試練のようなものをいつも感じています。すごく偉大な作曲家ですし、自分たちには思いもよらないことを考えてオペラをつくっていたんじゃないかなと。ヴェルディに「どうだ、歌えないだろう」と言われているような気がして。そこを、歌い手の人生をかけてそこを乗り越えていくところに、演者としての魅力があるのではないかと思います。
ー上江さんのようにご活躍の方でも、壁は毎回感じていらっしゃるのですか?
毎回です!ヴェルディの作品は、どんな役でも必ず壁があります。
ー具体的にはどういった壁なのでしょうか?
そうですね、お芝居と歌のバランスを取るのがすごく難しい、といいますか。一回出来たからといって二回目が出来るかというと、そういうわけにもいかないのです。そのときの体の状態や波長、自分が置かれている状況があるなかで、自分が出来るいちばんいいものを自分自身で感じ取らなければいけない。リゴレットという役も複数回演じていますが、どんなに回数を重ねても、毎度一から勉強するつもりで臨んでいます。昔がどうだったかというよりは、今出来ることを探して。これは折江総監督もおっしゃっていたことですが、一生懸命歌っている人というのは必ず挑戦していて、いつも自分にとってギリギリのところで闘っている、と。そういう感性を、私自身も常に持っていたいなと思います。
ー常に初心にかえって臨まれているのですね。今回は、どんな点にポイントをおいて役作りをしようと考えていらっしゃいますか?
ヴェルディのオペラはすごくメッセージ性が強いのですが、この『リゴレット』は、本当は「呪い」という言葉をオペラ・タイトルにしようかと考えていたといわれるぐらい、背負って生まれてきてしまった運命的なものを表現したかったのではないかと思うのです。リゴレットという人物の生き様もしかり、彼の娘であるジルダとの親子関係もしかり。私にも今度小学生になる娘がいまして、前回歌ったときにはまだ2歳ぐらいだったのですが、今回はそのときと娘に抱く気持ちが違います。もちろんジルダの歳にはまだ早いですが、幼かった頃に比べて、より心配になる気持ちや、将来どうなるのだろうと考える気持ちが増したことは、リゴレットの深い部分に近づけるかなと思います。 それから、これはイタリアの話ですが、とある有名なリゴレット歌いの方が、公演の一週間前ぐらいに交通事故で娘さんを亡くしてしまわれた。それでもやっぱり歌い手として歌わなければいけなかったから、本番ではオーケストラもお客さんも劇場中が泣きながらやっていたといいます。その話を聞いたとき「すごいことをやっているなぁ!」と思いましたが、それぐらい、自分の中に持つものをひとつの表現として昇華させなければいけないのだと思いました。そこがリンクしたときに、ものすごいものが現れる可能性を持っている。ただのお涙頂戴ではなく、親子関係にしても、運命的なものにしても、本質的なものが表現されている作品なのだと感じています。運命的なものといえば、リゴレット自身が背負っている運命のような部分も表現できたらと思いますが、たとえば彼は生まれつき体に不具を負っていた。これは、このオペラが生まれた当時は、舞台に乗せてはいけない題材と考えられていたようですが、ヴェルディはこういう人たちもいるんだよ、この人たちの運命や人生を共有しよう、そしてみなさんも考えてくださいという提示をした。その、背負って生まれてきたもの、変えられない運命的なものをどう表現していくかがこのオペラの興味深いところです。

ーその人が背負っているもの、運命的なもの、という題材は、ヴェルディ作品には多く見られますよね。
『リゴレット』を作曲したこの時期は、『ラ・トラヴィアータ』や『イル・トロヴァトーレ』など、特にそこに焦点を当てた作品が多いかもしれませんね。ヴェルディ自身も“運命”のような題材に惹かれていたのかもしれませんし、こういった提示を行うことで後世まで残っていくような作品になると予感していたのかもしれません。今でこそクラシックの領域ですが、当時としては最先端をいこうとしていた人々なので。
ー当時の最先端であり、問題提起であり、本質的な表現を要求する芸術作品でもあったのですね
そうですね。「いい作品をつくらなければ」とよくいわれますが、「いい作品」というより「本質的な作品」になるよう、うまくいくかいかないかはともかく、歌い手ひとりひとりがそのとき出来る最高のものを出そうという意識を持って、みんなでつくり上げていく。それがヴェルディのオペラに臨むときの姿勢であるべきかなと思います。
ヴェルディのオペラに求められるのは、歌い手と演じ手のバランス。
ー上江さんが考える『リゴレット』の見どころはどちらですか?
そうですね、たくさんあって選ぶのが難しいですが、あえて一つあげるなら、終幕、最後の場面でしょうか。自分の娘が、自分の仕えるマントヴァ公爵に汚されたということで復讐を試みますが、公爵の死体だと思ってよく見てみると自分の娘が公爵の身代わりになって死んでいた。その娘の死を目の当たりにしたときのリゴレットの気持ちというものが音楽で表現されているのですが、そのメロディーがものすごくきれいなのです。小鳩が空に羽ばたいて行くかのようなその美しいメロディーを、その場面の心境で歌わなければいけないのがものすごくつらくて。でも、それだけに一番印象にも残ると思うのです。私自身はその場面がもっとも好きですし、演者としてやりがいのあるところだと思います。そこで、さっきお話しした“本質”をいかに表現できるかを追求してみたいですね。
ー最後のシーンですか。
はい。娘は自分のところから離れていってしまい、何もかもから突き放されて孤独になってしまう。
ー唯一の心の支えだった娘・ジルダが離れていってしまう。本当に孤独でしょうね。
そうなのです。その娘も、ストーリーとしてはずっと一緒に住んでいたわけではなく、呼び寄せて3、4ヶ月ぐらいしか暮らしていないので、その前のリゴレットはずっと孤独だったはずなのです。彼のような宮廷付きの道化師というのは、占い師などのようにちょっと人とは違う能力を使える人と考えられていて、その代わり身体にどこかしら障害を持っている人も実際に多かったようなのです。そうすると、貴族に仕えているので身分もお金もそれなりにあるのですが、人として見なされない。肖像画に描かれるときも、必ずペットと同じ位置に描かれる。そんな扱いをされていたのです。でも、リゴレットにはそれしかできない。貴族たちが、政治的に悪い事を言わなければならないような場面でも自分たちが傷つかないために、道化師に悪口を言わせ、あざ笑わせる、そのための道具になるしかなかった。
ーそんな彼が心の慰めである娘を失った悲しみは、計り知れないでしょうね。それにしても、お話を聞けば聞くほど、先ほど上江さんが“壁”とおっしゃっていた「歌い手と演じ手のバランス」の実感が増してきます。
はい。この時期ヴェルディは『リゴレット』『イル・トロヴァトーレ』『ラ・トラヴィアータ』という3つのオペラを作曲しているのですが、これらの作品より前は、通称「番号オペラ」といって、1番:何々のアリア、2番:何々のカヴァレッタ…という伝統的なオペラの作曲スタイルだったのですが、『リゴレット』からはそれが急になくなるのです。アリアやカヴァレッタといった音楽と音楽がより劇的に進行するようにつながって、この作品は特にお芝居の要素がものすごく強くなったのです。私もたくさんオーディションなどでこの作品のアリアを歌いましたが、先ほどのラストシーンのアリアは、感情的になりすぎると声が出なくなって歌えないこともある。でも、芝居を求める人にとってはそれぐらいがよしとなるし、音楽を求める人にとっては「それはやりすぎだ」ということになる。演じることと歌うことが、絶妙に共存していないといけないのですね。
ーなるほど。そのさじ加減は、共演者の方々によっても変わってくると思うのですが、今回ご一緒したことのある方はいらっしゃいますか?
ジルダ役の光岡暁恵さんは、ご一緒したことがありますね。ちょうど1年前の『ラ・トラヴィアータ』で、光岡さんがタイトルロールのヴィオレッタで私がジェルモンでした。稽古が大変楽しかったです。マントヴァ公爵役の村上敏明さんもお仕事でご一緒しました。でも役としては、リゴレットと絡みがあるようでいてあまりなく、最初だけなのですよね。リゴレットは孤独な役なのです(笑)。やはり光岡さんのジルダが唯一関わりが多いと思いますが、幸いお互いの歌い方や癖なども知っています。また、音楽と芝居とのバランスの考え方も同じものを持っていると思うので、歩み寄っていけたらいいかなと思います。

ーそれでは、今回も素敵なコラボレーションが期待できますね。マエストロの柴田真郁さんとは、いかがですか?
柴田マエストロとは初めてのお仕事なのですが、歌のブレスを熟知されている方だなというのが印象的で。こちらの歌をすごくちゃんと聴いて合わせようとしてくださるので、かなり歌いやすいです。オペラ指揮者って難しくて、いろいろな人と関わらなければいけないから、自分の信念があって、自分の音楽を突き通すというだけでもダメで。声のことだったり、音楽のことだったり、なんでも知っていなくちゃいけなくて、みんなに信用されなくてはいけない。本当に“マエストロ”という感じですよね。そういった意味で、全体をよく見てバランスを取ろうとされている「オペラ指揮者」としての印象をすごく受けました。
ーそうなのですか!では、素晴らしい音楽が生まれること請け合いですね。演出家の松本重孝さんとも、初めてですか?
松本先生は、先日の『ランスへの旅』のときに初めてご一緒しました。松本先生もすごく柔軟性をお持ちで、その人の出来ることをよく見ていらっしゃる方だと感じました。あまりご自身から「こうして」「ああして」と多言はなさらないのですが、本当に必要なことをパッパッと言っていき、それでオペラが成立する。素晴らしい演出家さんだなと思います。

長らく拠点を置くイタリアでの、運命的なリゴレット・デビュー。
イタリアで勉強しているとき、ちょうど私の先生がリゴレット歌いの人だったのですが、練習をして本番に乗せられるぐらい仕上がったときに、「昔舞台での体の使い方を教えてくれた、自分の先生のところへ行くか」といわれて。結局、私に教えてくれているとき70代の先生が、勉強していた時代の先生なのでもう亡くなっていたのですが、「じゃあ俺が教える」といって興味深いポイントを教えてくれました。後天的な体の不具合を持った人というのは、もともと動いていた部分が動かなくなってしまいびっこをひくような形になるのですが、先天的に動かない部分を持って生まれた人というのは、それが普通のことなので動作も自然にしなければならない、というのです。イタリア語でも「Zuccone(びっこをひく)」と「Trascinare(引きずる)」というように言葉が区別されていて、生まれ持った自然な動作をつくることで、歌も楽に歌えるようになるんだよといわれました。後天的な動作のほうでは、どこかに力が入ってしまって歌もうまくいかなくなる。それを教わっただけでも、自分のなかではかなり解決したことが多かったですね。リゴレットの演技のヒントを得たと同時に、その奥深さを改めて感じました。
ーそのとき得たものが、現在の役づくりにもつながっているのですね。ところで上江さんは、今でもイタリアを拠点に活動されていると伺いました。聞くところによると、あと1回ビザを更新すると永住権が得られるとか。
そうなんです!8、9年はずっと向こうで生活していましたし、最近はほとんど日本にいることが多くなってきましたけれど、できれば永住権まで頑張りたいですね。現在はミラノですが、パルマにもちょっといましたし、さらにヴェルディの故郷であるブッセートの町にもコレペティートル(歌手に伴奏などをしながら音楽稽古をつけるピアニスト)の先生がいたので毎週のようによく通いました。最初に『リゴレット』を歌ったのもそのブッセートでのヴェルディ・フェスティバルで、しかも歌ったその日がヴェルディの誕生日だったのです。
ーそれはすごい!それもまさに運命的ですね!
はい、そのときはさすがに運命的なものを感じました!ちょっと面白い余談があって、「話がうまくいきすぎていて、なんだか気持ち悪いな」と思ったので、当時住んでいた部屋の下のおばあちゃんに良くイタリアのバールで売っているスクラッチくじを買わされていたのですが、そのついでに自分の分も買ってみたら、何と一枚で100ユーロぐらい当たったのです(笑)。「これはなんか怖いな」と。ある意味気合を入れ直して楽譜を開いたのを覚えております。(笑)そのときは現代的な演出で、あまりせむし男という感じでは演じなかったのですが、ブッセート劇場は満員になっても200名ほど、1階の平場の席は50席ぐらいという小さな劇場で。演じ手の息遣いも全部伝わるし、より臨場感の出る場所だったこともあり、より演劇的にやらせてもらってすごく勉強になりました。

ーそこで“演じるリゴレット”を吸収されたのですね。それにしても、長くイタリアにいらして、日本と違うなと感じた部分はありますか?
音楽に対する聴き方が違うな、とは思います。日本人はよく「オペラに慣れていない」といわれますが、私はそれって慣れてないというより、そこで鳴る音の感覚が違うのであって、また日常の生活習慣などによってそれを受け取る感性の違いじゃないかなと思いますね。もちろん言葉の違いは大きいでしょうけどね。日本では大きくて立派な声をつくることがまず第一条件になって、大きい劇場でも通用することを求められることが多いですが、イタリアでは小さい劇場ならではの繊細な表現を求められることもあったり。
ー寝て、起きて、食べて、日々を暮らすという活動自体は万国共通のはずですが、ちょっとした習慣の違いの積み重ねで、感性もそれぞれに育まれていくものなのですね。
そうですね。あと、日本では言いたいことがあったとしても言わないのが礼儀や美徳とされることがありますが、イタリアでそれをやると「自分の意見がなくて弱い人」だとみなされてしまう。面白いのは、たとえば遅刻をしたとき、遅刻自体はまぁいいとして、それに対して理由をちゃんと言えなければいけないのです。それは、ある意味嘘でもよくて(いいことではないですが)、内容が面白かったり筋が通っていればいいのですが、とにかく理由をきちんと主張するということを中学生ぐらいの頃から求められるのです。日本では、「言い訳はよくない」と捉えられてしまいそうな感覚ですが、面白いですよね。
ーそうなのですか!それは興味深いですね!ところで、上江さんはイタリアでオフの時間は何をして過ごされますか?
私は釣りが好きなので、オフには釣竿を持って出掛けますね。湖や海に行って、趣味として食べられない魚も釣りますし、食べられる魚が釣れたときは自分で料理もします。

ーご自身で料理もされるのですね。どんな料理をよくつくるのですか?
そうですね、日本食もつくりますが、私はイタリアに行く前にイタリア料理屋でバイトをしていたので、その経験を生かしてたイタリア料理が多いですね。素材の味がすごく大事なのですが、ちょうどミラノの家の前に市場が立つので、新鮮な食材を買ってきて、本場のイタリアの食材で季節の料理をつくるのです。
ーお料理、お上手そうですね。貴重なイタリア生活のお話、ありがとうございます。
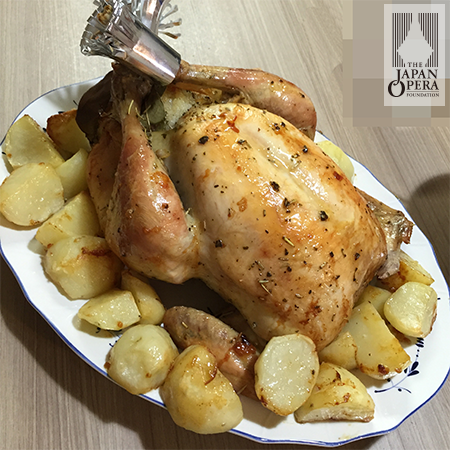

聞いてみタイム♪
アーティストからアーティストへ質問リレー。
丹呉由利子さん&長島由佳さんから、上江隼人さんへ。
ー歌手から歌手への質問コーナー「聞いてみタイム」、今回は、丹呉由利子さん&長島由佳さんのおふたりから、上江隼人さんへのご質問が届いています。

ーアスリートから学ぶことは何ですか?
アスリートですか。そうですね、私たちの仕事は声を使うわけですが、そのためには体もよく鍛錬しなければいけないので、そこがアスリートと同じですね。毎日声を出したり、声づくりのために体の調整をしたり。でも、オリンピックやスポーツのワールドカップを見ていると、いい記録を出す人たちって、やっぱり精神的に負けないですね。その「負けない」という気持ちが、特に歌い手と重なる部分だと思います。たとえば今回の『リゴレット』のように大変な作品を歌わなければならないときに、いかに自分の信念を貫いて、最後まで諦めないでいけるかということを、音楽の上で大事にしています。
ーメンタル的な強さが、特に通じる部分なのですね。上江さんは、学生時代ずっと剣道に打ち込まれていましたよね。
はい。剣道も武道なので、精神性のような部分も強いですね。剣道は剣を極めるために、歌い手は歌を極めるために進んでいくところが同じだと思います。だから、他のスポーツのアスリートからも、スポーツを極めるために自分を信じて進む強さが大事だと再認識します。スポーツって勝ち負けの結果がはっきりと出ますが、昨年のラグビーや、オリンピックに向けた様々な試合でも、勝ったときも、負けたときでさえも「また次の試合に向かっていかなければ」と選手がインタビューに答えますよね。「ああ、自分の歌に置き換えても、その精神性は大切だなぁ」と感じますね。
ー自分を信じて進む強さに、共通点を見出されるのですね。ありがとうございました。
取材・まとめ 眞木 茜
